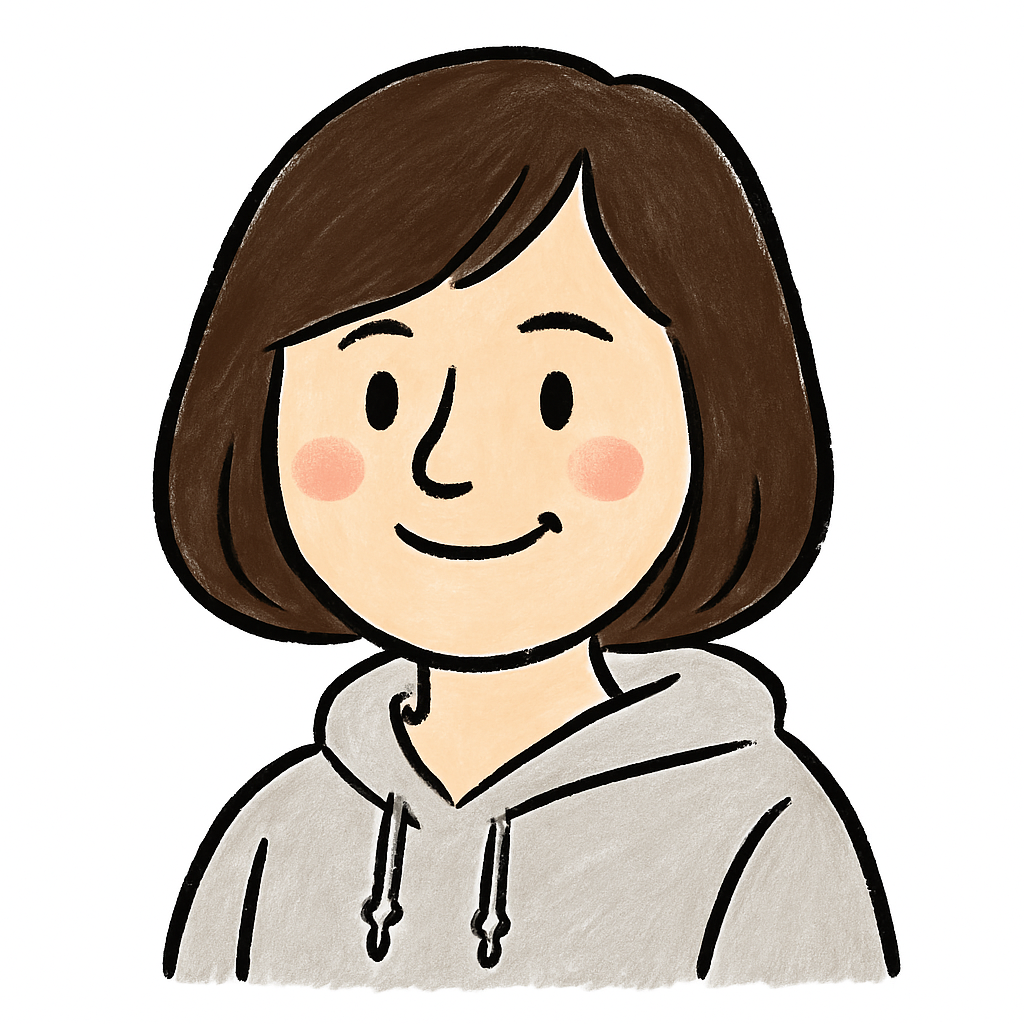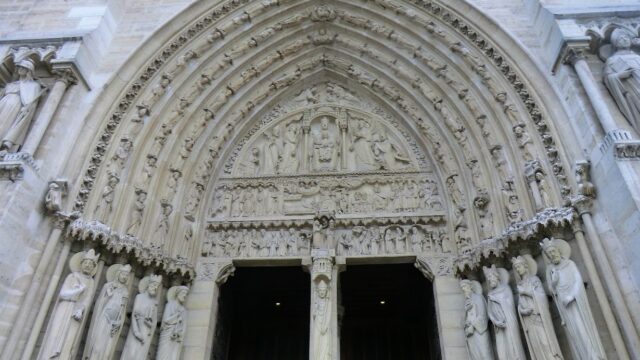「ダブルインカム」と聞いて、何を思い浮かべるでしょうか?
共働きで収入に余裕があり、自由度の高い生活を送っているDINKs(Double Income No Kids)──
そんな“ライフスタイル”を思い浮かべる人が多いかもしれません。
たしかに、夫婦ふたりが働いて収入を得るというのは、経済的には強い。
けれど、“人的資本”だけに依存するダブルインカムには、構造的な限界があると、ぼくは思っています。
なぜなら、働いて得る収入は、自分の時間と労力を前提とした「有限の資源」だからです。
もし片方が病気になったら?育児や介護で仕事を減らしたら?
そのとき、もう片方の労働だけで家計を支えきれるでしょうか。
では、もし夫婦それぞれが“投資”というもう一つの収入エンジンを持っていたら──?
それは、単なる「ダブルインカム」ではありません。
人的資本 × 金融資本のクロス構造による、4本の収入軸──つまり“クアトロインカム”と呼ぶべきかもしれません。
もちろん、夫婦共働きで投資もしている世帯は、すでにたくさん存在しているはずです。
決して目新しいことではありません。
けれど、その構造にきちんと名前を与え、意味づけし、ライフデザインとして再定義することには価値がある。
だからこそ、本記事では「クアトロインカム」という新たな概念を、ぼく自身の資産形成と自由設計の視点から提案してみたいと思います。
言葉を名づけることで、見えてくる“生き方”のかたち。
夫婦で人生を設計しようとするすべての人に、ひとつのヒントになれば嬉しく思います。
第1章|世の中の「ダブルインカム」は、なぜ“足りない”のか?
「夫婦で共働きだから、うちはダブルインカムです」
そう語る人は多く、たしかに収入源が2本あることは家計の強みになります。
けれど、その2本がどちらも“人的資本”に依存しているとしたら──
それは、本当に十分な構造と言えるのでしょうか。
人的資本とは、自分の時間や労力を提供して得る収入、つまり「働いて得るお金」のことです。
会社員でも自営業でも、フリーランスでも、自分が動いて初めてお金が生まれる仕組み。
だからこそ、もしどちらかが病気になったり、育児・介護などで働けなくなったりすれば、
一気に“2本のうち1本”が失われてしまうリスクを抱えています。
たとえ今は二人とも健康で、キャリアも順調だったとしても、
人的資本による収入には明確な“上限”があります。
働ける時間には限りがあり、年齢とともにパフォーマンスは変化していく。
ライフステージの変化──出産、育児、介護、転職など──は、収入のペースを左右します。
そしてもうひとつ。
人的資本に頼るダブルインカムには、自由が手に入りにくいという落とし穴もあります。
働く時間を増やせば収入は増える。
でもそのぶん、自由な時間は減っていく。
逆に、時間に余裕を持とうとすれば、収入は減る。
この「時間とお金のトレードオフ」から抜け出すことができない構造なのです。
表面的には豊かに見えても、実態はとても脆い。
「どちらかが働けなくなったら家計はどうなる?」という問いに耐えうる構造にはなっていないのです。
ぼくたちは、資本主義というルールの中で生きています。
そのルールは明快です。
「リスクを取って資本を投じた人がリターンを得る」──それが社会の構造そのもの。
つまり、人的資本だけに頼る働き方は、
資本主義というゲームで“片翼だけで飛んでいる”ようなものなのです。
たとえば飛行機でいえば、本来2基のエンジンで飛ぶ設計になっていても、
片方のエンジンだけで飛べるのは非常時の措置。
安全は確保されても、推進力や操作性には限界が出る。
本来の設計通りに“両翼のエンジン”を使ってこそ、安定した飛行が可能になるのです。
ではもうひとつのエンジンとは、いったい何なのか。
そして、それはどうすれば手に入れられるのか。
次章では、“金融資本が働く”というもう一つのエンジンについて、掘り下げてみたいと思います。
第2章|“もうひとつのエンジン”──金融資本が働くということ
人的資本に頼るダブルインカムでは、
「働かない=稼げない」という構造から抜け出すことができません。
だからこそ、ぼくたちはもうひとつの収入源──
“金融資本”というエンジンを持つべきだと考えています。
お金に働かせる、という発想
投資と聞いて、多くの人がまず思い浮かべるのは「リスク」かもしれません。そんなふうに考えて、次のような言葉が口をついて出てくることもあります。
- 「損するかもしれない」
- 「よくわからないから不安」
- 「うちは共働きで十分だから投資までは……」
- 「夫は投資したいけど、妻は反対していて」
こうした感情は、とてもよくわかります。
特に夫婦で投資への認識にズレがあると、最初の一歩を踏み出すまでに、どうしても時間がかかってしまうものです。
でも、資本主義というルールの中で暮らしている以上、
「お金に働いてもらう仕組み」を持っている人が、構造的に優位に立つ──
これは紛れもない事実です。
たとえば、株式や投資信託、不動産などに資本を投じておけば、
そこから配当や値上がり益といったかたちで「お金が収入を生む」状態が生まれます。
つまり、自分が寝ていても、お金は働き続けてくれる。
もうひとつのエンジンが、静かに家計を支えてくれるのです。
投資は、自由を得るための“仕組み”
ぼくたちは、働いて得たお金を消費だけに回すのではなく、
未来の自由のために「資本化」することができます。
これは、単なる資産形成ではありません。
「自由を設計する」という考え方そのものです。
- 働きすぎたら、投資の収入で“時短”という選択肢ができる
- 夫婦のどちらかが休職しても、家計が崩れない
- 子育てや介護の時期にも、生活を支える“時差収入”がある
- 将来、早期退職して旅に出ることも可能になる
こうした柔軟性は、人的資本だけでは手に入り辛い、“構造としての自由”です。
投資=ギャンブル、は本当か?
たしかに、投資にはリスクがあります。
けれど、リスクがあるからといって避け続けていては、
資本主義社会の「構造的恩恵」を自ら放棄してしまうことになる。
むしろ大切なのは、
「どこに、どのように、どんなリスクで投じるか」
を理解し、感情ではなく構造で投資を捉えること。
そうすれば、ギャンブルではなく「自由のための合理的選択」としての投資が見えてきます。
それが、ぼくたちshisan-tabiの投資観です。
人的資本 × 金融資本
この2つが揃って、ようやく本来のダブルエンジンが回り始める。
そして、もしこの“2本の収入源”を夫婦それぞれが持っていたとしたら──
その家計は、構造的にどう変わるのか?
次章では、その拡張されたライフスタイル設計、
「クアトロインカム」という新たな家計モデルについて提案してみたいと思います。
第3章|そして、本業×副業ではない。「市場×市場」で考える“クアトロインカム”──夫婦で“4本の柱”を持つという設計
夫婦で共働き。
それだけでも「ダブルインカム」としては十分に聞こえるかもしれません。
けれど、もしその二人がそれぞれ金融資本のエンジンも持っていたとしたら?
人的資本 × 金融資本 × 2人分──
つまり、4本の収入源が家計を支える構造になります。
この拡張された家計モデルを、ぼくは「クアトロインカム(Quattro Income)」と名付けました。
※「クアトロインカム」という言葉には、実は複数の解釈があります。
たとえば「共働き+副業」の4軸モデルとされるケースもありますが、本記事で扱うのは、「労働市場(人的資本)×金融市場(投資)」という“2つの市場”に夫婦でアクセスする構造的視点です。「副業の有無」ではなく、「市場へのアクセス構造」そのものが焦点になります。
クアトロインカムの構成とは?
クアトロインカムとは、次のような4つの柱から成り立ちます:
- 夫の労働収入(人的資本①)
- 夫の投資収入(金融資本①)
- 妻の労働収入(人的資本②)
- 妻の投資収入(金融資本②)
それぞれが人的資本と金融資本の2本のエンジンを持ち、家計全体では4本の推進力を備えている──
この構造は、安定性・再現性・柔軟性の面で大きな強みを発揮します。
なぜ「4本のエンジン」が強いのか?
たとえばこんな場面で、クアトロインカムの強みが発揮されます:
- 一人が病気や転職で一時的に収入を失っても、他の3本で家計を維持できる
- 子育てや介護で、片方がキャリアを一時中断しても、投資収入が“時差的”に家計を支える
- 将来どちらかが早期リタイアしても、片方の人的資本と二人分の金融資本で暮らせる設計ができる
つまり、これは単なるリスクヘッジではなく、夫婦の人生に“しなやかさ”と“選択の自由”を与える構造なのです。
A380のような家計モデル
旅客機にたとえるなら、一般的な飛行機が2基のエンジンで飛ぶのに対し、
世界最大の二階建て旅客機A380は、4基のエンジンでより多くの搭乗客を、より遠くまで運ぶことができます。
同じように、クアトロインカムという家計構造は、
二人で人生というフライトを遠く・長く・自由に飛び続けるための“設計思想”なのです。
夫婦の会話も変わってくる
金融資本を夫婦それぞれが持つようになると、家計管理の会話もより戦略的になります。
- 「世帯全体の投資パフォーマンス、今どれくらいになってるかな?」
- 「新NISAの枠、来年から増額できそうだね。戦略ちょっと練り直す?」
- 「教育費は、このまま15年くらい積み立てていけば安心できそうだね」
こうした会話は、単なるお金の話ではありません。
未来をどう設計するかという“共同経営”の視点が生まれるのです。
ぼくたちshisan-tabiの家庭では、子どもを持たないDINKsとして、すでにオルカン(全世界株)投資を実践しており、
もはや日常の会話はこうなります:
世界一周旅行、人生で何回できるかな?
2028年といわず、すぐにFIREしない?
これは家計の会話ではなく、
生き方の選択肢そのものを、夫婦で語れるようになった証拠かもしれません。
クアトロインカムという発想は、
夫婦が“生活の共同体”であるだけでなく、“設計の共同体”になるための土台でもあります。
次章では、このクアトロインカムがもたらす自由の設計思想について、
shisan-tabiの核心と接続しながら、もう一歩深く掘り下げてみたいと思います。
第4章|これは“自由の設計図”である──クアトロインカムと生き方の再構築
「自由に生きたい」
それは誰もが一度は願うことかもしれません。
けれど、その“自由”が、感情ではなく構造によって左右されるものだと気づいている人は、案外少ないのではないでしょうか。
自由とは、「やりたいことをすること」ではなく…
shisan-tabiでは、自由を「やりたいことをやれる状態」ではなく、「やりたくないことをやらずに済む状態」と定義しています。
一見同じように思えても、この違いは大きい。
自由は、意志の強さで手に入るものではありません。
お金・時間・暮らしの構造が整っていて、初めて手に入る設計された結果なのです。
「旅したい」「会社を辞めたい」──そう思ったとしても、
その基盤がなければ、それはただの“願望”に過ぎません。
クアトロインカムは、自由を構造的に実現する
クアトロインカムは、単に収入を増やすためのモデルではありません。
それは、自由という抽象的な理想を、家計という現実の構造に埋め込むための設計図なのです。
- どちらかがキャリアを一時中断しても、家計は崩れない
- 投資エンジンが生む不労収入が、日常に時間の余白を生む
- 夫婦それぞれが「選べる力」を持てるようになる
この構造がもたらすのは、単なる防御力ではありません。
変化にしなやかに対応できる、“戦略的な柔軟性”です。
クアトロインカムは「ひとつのモデル」にすぎない
もちろん、すべての家庭がクアトロインカムを実現できるわけではありません。
けれど、この構造を「知っている」かどうかで、人生の選択肢は大きく変わります。
この構造が、家庭ごとにどう異なりうるのか──
補章では、共働き・片働き、子どもの有無、投資の有無といった観点から、10通りのパターンに整理してみました。
家計構造と自由、すなわちFIREの“難易度”の関係が、よりクリアに見えてくるはずです。
次章では、こうした構造に“名前をつけること”──
つまり、「まだ言葉になっていない生き方」を定義するという試み自体について、ぼく自身の視点からまとめてみたいと思います。
おわりに|クアトロインカムを“名づける”という冒険
クアトロインカム──
この言葉は、今のところ辞書にも経済誌にも載っていません。
けれど、ぼくはあえてこの言葉をつくり、定義してみようと思いました。
なぜなら、まだ名前のついていない構造に言葉を与えることは、
そのまま“生き方に輪郭を与える行為”だと思うからです。
言葉にすれば、構造が見える
多くの人は、「共働きが安心」「投資が必要」と、なんとなく感じています。
けれど、それがどんな構造で、どんな意味を持つのかまでは、
言語化されていないことが多い。
「クアトロインカム」という言葉があれば──
夫婦それぞれが人的資本と金融資本のエンジンを持ち、
家計全体が4本の収入軸で支えられている状態が、明確にイメージできます。
それは、VUCA(ブーカ)と呼ばれる将来予測が極めて難しい不安定な時代において、自分たちの人生を“設計”するための骨組みを持つということ。
構造が見えるからこそ、戦略も描ける。
そして、戦略があるからこそ、自由に近づける。
名づけることは、選びとること
これは単なる造語・言葉遊びではありません。
世の中にまだない概念に、自分の手で名前をつけることは、
その生き方を「選びとる」という覚悟の表明でもあるのです。
誰かが敷いたレールの上を歩くのではなく、
まだ地図のない領域に、仮の道を描き始める。
そんな静かな冒険が、人生を少しずつ自由にしてくれる──
ぼくはそう信じています。
クアトロインカムという言葉を、これから育てていく
この記事で提案した「クアトロインカム」は、まだ“はじまりの名前”です。
定義はこれから少しずつ磨かれていくだろうし、
夫婦のかたちや人生のステージに応じて、柔軟にアレンジされていくはずです。
でも、こうして名前を与えたことで、
構造が言語化され、選択肢として自分たちの人生に取り込めるようになった。
それだけでも、この試みには意味があると思っています。
生き方に、名前をつけよう。
クアトロインカム──
それは、自由を設計する夫婦の、静かで力強い選択肢。

補章|自由設計の難易度を“構造”で見てみる──10の家計モデルから考える
本編では、「クアトロインカム」という構造を通して、夫婦が自由を設計するための収入構造について考えてきました。
ここでは補章として、世帯構成・投資の有無・子どもの有無という三つの軸で、代表的な10の家計モデルを整理し、“自由の難易度”を構造的に見える化してみたいと思います。
これは、shisan-tabiが重視してきた「構造で自由を設計する」という思想を、具体的なパターンに落とし込んで可視化する試みです。
| ケース | 世帯構成 | 就業状況 | 投資状況 | 子ども | FIREの難易度 | 構造の特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 夫婦 | 共働き | 夫婦ともに実施 | なし | ★☆☆☆☆(Very Easy) | 人的+金融の4本柱。自由設計の理想形。 |
| B | 夫婦 | 共働き | 夫婦ともに実施 | あり | ★★☆☆☆(Easy) | 4本柱だが教育費など支出増。構造は安定。 |
| C | 夫婦 | 共働き | 片方のみ実施 | なし | ★★★☆☆(Normal) | 人的資本×2+金融資本×1の3本構成。 |
| D | 夫婦 | 共働き | 片方のみ実施 | あり | ★★★★☆(Hard) | 教育費増に対し、金融資本が不足しがち。 |
| E | 夫婦 | 共働き | 投資なし | なし | ★★★★☆(Hard) | 2本柱のみで、柔軟性に欠ける構造。 |
| F | 夫婦 | 共働き | 投資なし | あり | ★★★★★(Very Hard) | 教育費負担+金融資本なし=最も厳しい構造。 |
| G | 夫婦 | 片働き | 実施あり | なし | ★★★☆☆(Normal) | 人的+金融でバランスが取れれば安定。 |
| H | 夫婦 | 片働き | 実施あり | あり | ★★★★☆(Hard) | ひとりで全て支える構造でリスク高め。 |
| I | 独身 | ― | 投資あり | なし | ★★☆☆☆(Easy) | 人的+金融で2本柱。支出低く自由度高い。 |
| J | 独身 | ― | 投資なし | なし | ★★★★★(Very Hard) | 単独の人的資本のみ。設計の柔軟性に乏しい。 |
📝 補足|この表にない構造も、もちろん存在する
このマトリクスは、代表的な構造を整理したものです。
当然ながら、すべての家庭や人生のかたちを網羅しているわけではありません。
たとえば──
「独身 × 子あり(ひとり親)」という構造は、人的資本が1本しかなく、かつ育児という重い責任とコストを背負うため、構造的には最も難易度が高いモデルの一つです。
けれど、だからこそ大切なのは、構造を知り、現実を把握した上で設計していくという視点です。
🧭 このマトリクスをどう使うか?
この表は、あなたの家庭や人生の構造を「自由の視点」で俯瞰するための一つのツールです。
FIREやゆるやかなセミリタイア、ライフシフト、副業、家族の時間、旅──
何を目指すにしても、まずは自分の構造を知ることが出発点になります。
- 自分はいま、何本の収入エンジンを持っているか?
- 将来に向けて、どんな組み合わせを目指すのか?
- パートナーとどう協力し、構造を変えていけるか?
こうした問いを、読者それぞれが自分の立場に置き換えて考えるきっかけになればと思います。




旅のプランニングと資産設計を通じて、自由な人生を構造的にデザインすることを追求中。
50歳での早期退職を目指し、世界一周航空券での長期旅を本気で準備しています。
思想・構造・実践──人生を支える「資産としての旅」を記録・発信中。