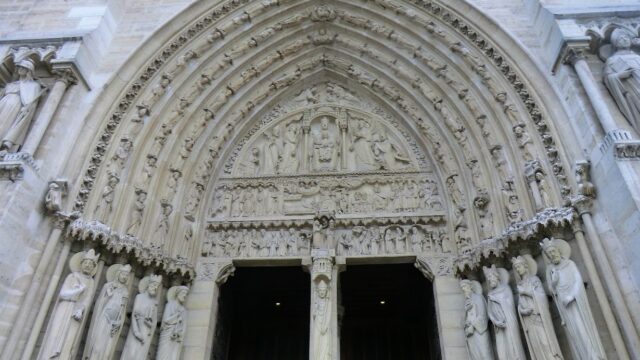「副業しないと」──そんな声を耳にすることがあります。
でも、本当にそうでしょうか?
経済学者トマ・ピケティが示した「r > g」(資本収益率 > 経済成長率)は、資本主義の本質を言い当てた有名な公式です。そしてこの公式が意味するのは、「働くより、資産を持つことの方が強い」という冷静な現実でもあります。
ぼくたち夫婦は、本業と投資の“4本構成”で暮らしています。
これは、副業をしないクアトロインカム。
けれど、この戦略こそが最もシンプルに、かつ力強く“自由”に近づける道だと考えています。
本記事では、r > gという資本主義の構造をベースに、「なぜ本業×投資だけで十分なのか?」を分解していきます。
第1章|“収入の本数”ではなく“構造”で考えるということ
「収入源は多い方がいい」──
これは誰もが納得しやすい考え方です。副業が解禁され、投資も一般化した今、3本、4本と収入源を増やすことは当たり前の戦略になりつつあります。
けれど、本当に問うべきは、“数”ではありません。
どの市場(労働市場か金融市場)にアクセスしているか──
つまり「どこからの収入なのか」を見極めることが、将来の自由度を大きく左右するのです。
ぼくたち夫婦は「クアトロインカム」という形で、
- 本業(会社員)
- 投資(インデックス投資)
をそれぞれが持ち、労働市場と金融市場に夫婦2人で参加しています。
収入の“本数”に目が行きがちですが、注目すべきは「r > g」の構造。
ピケティが示したこの不等式は、資本(=投資リターン)が労働収入を上回るという構造的な力学を示しています。
つまり、投資というエンジンを積むことは、時間的・経済的自由を支える“構造そのもの”の強化に他なりません。
副業のように時間を切り売りする必要もない。
本業も、昇進昇格をある程度まで狙って効率的に達成し、あとは定時退社+フル有給消化を実現できれば、生活は一変します。
投資がrで回り続ける限り、ぼくらはgを超える自由を手に入れられる。
この戦略こそが、“本業×投資”によるクアトロインカムの本質的な強さなのです。
第2章|r > g──なぜ“投資”という構造が優れているのか
経済学者トマ・ピケティが示した「r > g」という不等式。
これは、r(資本収益率)がg(経済成長率)よりも恒常的に高いことを示しています。
言い換えれば、
“労働による所得より、資本が生むリターンのほうが強い”
という、資本主義に内在する構造的なルールを表しています。
投資は「自分の時間を使わずに増える」構造である
本業や副業は、基本的に自分の時間を投入しなければ報酬を得られません。
しかし、投資というのは“お金が働く”仕組み。
インデックス投資を例にとると、以下のような利点があります。
- 放置で増える(手間がかからない)
- 世界経済の成長を取り込める
- 長期だと複利効果が効いてくる
だからこそ、我が家では副業には注力せず、
「人的資本は本業に集中。余剰資金はすべて金融資本に変換」
というシンプルかつ強い戦略をとっています。
時間と労力(エネルギー)を“有限資源”と捉える
副業を含めて“本数”を増やす戦略には、物理的・精神的な制約があります。
- 自分時間を必要とし疲弊する
- 生活に余白がなくなる
- 継続するために情熱が必要
一方で、インデックス投資は再現性と持続性を備えており、
「資本収益率で労働収入を凌駕する」r > gの構造を、誰でも取り込める道を開いてくれるのです。
“r > g”の世界で設計するクアトロインカム
ぼくたち夫婦のクアトロインカムは、副業を含めていません。
その理由は明快です。
- 投資(r)は労働(g)よりパワーがある
- 投資は自分時間を必要としない
- 投資は複利で伸び、再現性が高い
だからこそ、「本業×投資」だけで十分に4本のエンジンを成立させ、
“自由な時間”と“資産の成長”を両立できるのです。
第3章|ポートフォリオを“夫婦で完全統一”するという合理性
世帯で資産形成を進める上で、
「夫がオルカン」「妻は債券」
「夫が攻め」「妻は守り」といった分散型の役割分担を目にすることがあります。
一見、バランスよく思えるこの戦略──
しかし、本当に合理的な態度とは何か?
ぼくたち夫婦の答えは明確です。
「完全に同一のポートフォリオを、夫婦で世帯で共有する」
統一こそが、最もシンプルで再現性のある設計
オルカン(全世界株インデックス)を核に据えた我が家のポートフォリオは、
リスク許容度・長期の期待リターン・投資方針がすべて夫婦で完全一致しています。
この設計のメリットは明白です。
- 資産全体を世帯単位で一体管理できる
- 運用方針のブレがなく、議論や摩擦がない
- どちらかが万が一のときも、戦略が引き継げる
つまり、シンプルで透明性があり、長期にわたって強いのです。
役割分担ではなく、設計の“共通言語”を持つ
夫婦で異なる戦略を取ると、どちらかが思わぬ損失や過度なリスクを背負う可能性が生まれます。
それに対して、同一戦略ならば──
- リスク共有が可能
- 管理コストも手間も削減
- 投資判断の全体最適化が可能
我が家では、資産運用についても「共同経営者」として扱っており、
どちらかの“個人の趣味”ではなく、世帯の戦略として整合性がとれた判断を徹底しています。
合理性の極みは「迷わないこと」
戦略を一つに統一することは、日々の意思決定のストレスを減らすことにもつながります。
- 積立額の調整
- 銘柄の選定
- 資産比率のリバランス
これらをすべて一つの判断軸で回せるからこそ、時間もエネルギーも奪われないのです。
投資において「最適解」は人によって違います。
しかし「最も再現性のある、強くてシンプルな戦略」を採用するなら──
ファイナンス理論に基づく投資を行うなら、夫婦共に同じ理論を信じて投資する。
夫婦で同じ戦略を共有することほど合理的な態度はないと、ぼくたちは考えています。
第4章|人的資本から金融資本へ──戦略的リタイアのデザイン
本業×投資を続けていると、人生のある時点で、
「もう働かなくてもいいかもしれない」と感じる瞬間が訪れます。
けれど、それは突然降ってくるものではなく、
戦略的に“設計”して、段階的に迎えるものなのだと、ぼくたちは考えています。
人的資本は、いずれ消える資本
人的資本とは、ざっくり言えば「労働によって得られる将来の収入・稼ぐ力」です。
健康で、若く、スキルや経験が活かせるうちは、この人的資本が主なインカム源になります。
でも──
人的資本は加齢とともに価値が減り、いつか必ずゼロになります。
だからこそ、まだ人的資本が強い段階で、
それを金融資本へと“変換”していく必要があります。
クアトロインカムの本質は「変換装置」にある
ぼくたち夫婦にとって、クアトロインカムとは「ゴール」ではありません。
むしろ、“通過点”であり、“変換装置”です。
- 本業で得た収入 投資へ
- 投資から得られた 収益再投資へ
こうしたサイクルを回しながら、
人的資本を金融資本へと段階的にスライドさせていく。
これが、戦略的リタイアへの一丁目一番地になります。
リタイア後もクアトロインカムは続く?
人的資本がゼロになった後も、収入は続きます。
- 金融資本からの資産運用収益
- 年金(公的・企業・iDeCoなど)
- 必要があれば、趣味を兼ねた副収入
たとえば、
夫:年金+投資収入
妻:年金+投資収入
これでも構造的には「クアトロインカム」
収入の“質”が変わるだけで、“構造”は維持できます。
つまり、クアトロインカムは人的資本の終焉後も持続可能なライフデザインでもあるのです。
最終目標は「自由時間の獲得」
ぼくたちが最終的に求めているのは、収入の多寡ではありません。
それは──「時間の自由」です。
- 定時で終わる仕事を選ぶ
- 投資は放置できる戦略を採用する
- 役職や昇進に執着しすぎない
こうして、少しずつ自分の時間を取り戻し、
早期リタイアによって完全な時間支配を手に入れる──
これが、クアトロインカム戦略が導く本当の価値だと、ぼくたちは信じています。
第5章|r > gという原理──資本の論理が人生戦略を変える
「r > g」──
経済学者トマ・ピケティの著書『21世紀の資本』で広く知られるようになったこの不等式は、ぼくたち個人にとっても、極めて重要な“人生のルール”を示しています。
「r > g」は資本主義の宿命
この式の意味は、次の通りです。
r:資本収益率(投資リターン)
g:経済成長率(所得の伸び)
そして、歴史的には「r > g」、
すなわち働くより、資産を持っていた方が豊かになれるという現象が一貫して確認されています。
これは、一部の富裕層や企業だけの話ではありません。
インデックス投資という手段が普及した今、
誰でも“rの世界”にアクセス可能になったのです。
本業はgの世界、投資はrの世界
この視点から見たとき、クアトロインカムの構造が持つ意味がより鮮明になります。
- 本業の給与所得は、g(=経済成長率)の世界で動く
- 投資からのリターンは、r(=資本収益率)の世界で動く
つまり、本業×投資のクアトロインカムとは、
gの世界で稼ぎながら、rの世界に移行していく構造そのものです。
投資を「攻め」と見なす時代はもう終わった
「投資はリスクがあるから…」というのは、投資を過度に恐れた考えです。
現代において、適切に分散されたインデックス投資(たとえばオルカン)を長期で保有し続けるならば、むしろ“安定的にrの世界に乗るための基盤”といえます。
そして、会社員であるということは、同時にgの世界の参加者でもある。
この両方の市場に夫婦で参加する構造こそ、まさにクアトロインカムの真価です。
※「r > gの意味や、なぜこの不等式が資本主義の本質を突いているのか」について詳しく知りたい方は、大和ネクスト銀行のコラム「富を築くために理解しておきたい『r>g』という不等式」もあわせてご覧ください。
第6章|本業×投資のクアトロインカムは“節税効率”でも最強
本業×副業ではなく、本業×投資──
この「クアトロインカム構造」が強いのは、単に“時間を奪われにくい”という点だけではありません。
税金や社会保険料といった制度の“構造”に対しても、極めて相性がいいのです。
夫婦でクアトロインカムを持つことで得られる3つの節税メリット
1.所得税・住民税が軽くなる
累進課税制度では、1人が年収1,000万円より、2人が500万円ずつの方が合計の税負担は軽くなります。
2. 社会保険料も分散で効率化
厚生年金・健康保険の保険料は個人単位で上限が設定されています。
2人で分散すれば、保険料の“無駄な重課”を避けやすくなります。
3. NISA非課税枠が2倍に
新NISAでは1人あたり年間360万円/生涯1,800万円。
夫婦なら年間720万円/生涯3,600万円の非課税投資枠を活用できます。
制度を組み合わせれば、老後の“出口”も非課税に近づける
さらに、投資による将来の取り崩しを考えるとき──
iDeCo(個人型確定拠出年金)や企業型DCを活用すれば、以下のような追加の節税効果が得られます。
- 掛金拠出時は全額所得控除
- 運用益は非課税
- 受取時も、退職所得控除や公的年金等控除で課税を抑えられる
つまり、“節税しながら、非課税で増やし、非課税または低税率で受け取る”という三段構えの戦略が成立するのです。
また、退職金についても、長期勤務であれば1,500万円程度までは課税ゼロで受け取れる退職所得控除が適用可能。
これらを活かすには、「計画的な退職」「資産設計との連動」が不可欠です。
投資は“r > g”の世界で生きている
トマ・ピケティが示した「r > g」(資本収益率 > 経済成長率)という構造的な力学。
金融資本で得られるリターン(r)は、人的資本(g)による昇進や昇給よりも、構造的に有利な土台を持っています。
その投資を、制度という“追い風”で非課税運用できる時代──
だからこそ、本業×投資のクアトロインカムは、「合理的な自由」へのもっともシンプルな道筋なのです。
税制度・投資制度を含めた「構造設計」こそが、人生戦略のレバレッジになる。
これが、ぼくたち夫婦がクアトロインカムにこだわる理由のひとつです。
最終章|自由とは「ルールを知り、設計すること」
「自由な人生を送りたい」──
そう願う人は多いでしょう。でも、自由は勝手にやってくるものではありません。
むしろ、自由とは自分の意志で設計するものです。
そしてその設計には、ルールを知ることが不可欠です。
自由を阻むものは「知らないこと」から始まる
たとえば──
- 「投資は怖い」と思い込んで、rの世界に参加しない
- 「副業は疲れる」と決めつけて、収入源を一本に固定する
- 「昇進なんて運次第」と思って、制度の仕組みを学ばない
このように、「知らない」が行動の障壁となり、また勉強しないことで、
結果として自由を遠ざけているケースは数多くあります。
ゲームに勝つには、ルールを知らなければいけない
サッカーをやるならルールを知る。
それと同じように、
お金のこと、制度のこと、資産形成の仕組みを知ることは、
この社会のゲームを勝ち抜くために欠かせない基本です。
ぼく自身、本業では社内の賃金テーブルや昇進条件を把握し、
「どこまで行けばいいか」を定めて戦略的に動いてきました。
そして投資では、長期でrの世界に身を置くという合理的選択を採った。
自由の土台は、知識と理解から生まれるのです。
目指すのは「早期退職」ではなく「自由の獲得」
早期退職やFIREは、あくまで一つの手段。
目指すべきゴールは、“何をしてもしなくてもいい状態”をつくること。
つまり、
- 人的資本(本業)でrの世界に入るための土台を築き
- 金融資本(投資)でrの世界に自動で参加し
- 最終的には、時間を最大限に自分のために使える
これが、自由の構造的な獲得だと考えています。
数ではなく構造を見よ。構造ではなく思想を問え。
セクスタインカムでもオクタインカムでもない。
本数を増やすことは自由の手段かもしれませんが、目的ではありません。
重要なのは──
- どの構造に身を置くのか
- どうやって自由を設計するのか
- そして、それは自分にとって納得できるか
自由とは、「最適なルールを、自分で選び取れる状態」です。
そのための収入構造設計こそ、shisan-tabiが発信する思想の中核です。
終わりに
「r > g」という現実を踏まえて、
本業と投資を軸としたクアトロインカムという構造を整える。
数に惑わされず、構造を読み解き、
ルールを知り、設計する。
それこそが──
自由に生きるための、最強の武器になると、ぼくは信じています。



旅のプランニングと資産設計を通じて、自由な人生を構造的にデザインすることを追求中。
50歳での早期退職を目指し、世界一周航空券での長期旅を本気で準備しています。
思想・構造・実践──人生を支える「資産としての旅」を記録・発信中。